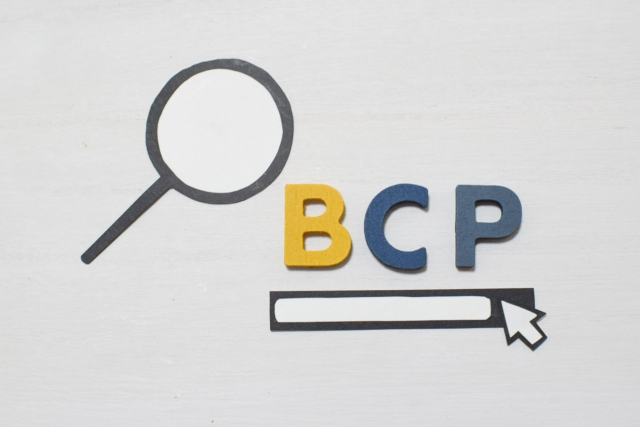
BCP対策とは、自然災害やサイバー攻撃といった不測の事態に備えて、被害からの復旧と事業継続を支えるための取り組みです。BCPを策定した上で適切に運用することで、初動対応を迅速に行い、事業への影響を最小限に抑えられます。
この記事では、BCP対策の基本と、実践のための重要なポイントについて解説します。
BCP対策とは? 事業継続計画の目的と基本概念
BCP対策は、自然災害や感染症の流行、システム障害といった緊急事態が起こった時に、重要な業務を継続できるようにするための対策です。ここでは、BCPの定義や策定の意義、BCPが重要視されている理由について解説します。
BCPの定義と策定の意義
BCPとは「Business Continuity Plan(事業継続計画)」の略称です。BCP策定の意義として、予期せぬ事態が発生した場合でも重要な業務の中断を最小限に抑え、速やかに復旧させることが挙げられます。
BCPの策定により、従業員の安全確保や経済的損失の最小化、取引先との信頼関係の維持を図ることが可能です。
なぜ今BCPが重要視されるのか(義務化や社会的背景)
近年、BCPが重要視される理由として、大規模な地震や台風、パンデミックなど多くの災害が起き社会全体での危機管理意識が高まっていることが挙げられます。これらの事態に備えるための施策として、BCPの策定や運用が欠かせません。
内閣府では事業継続ガイドラインを策定し定期的に改訂を行っているほか、2024年4月からは介護事業者へのBCP策定が義務化されました。
BCP対策の基本プロセス「4つのステップ」
BCP対策の基本的なプロセスは以下の4ステップです。
- 中核業務を特定し優先順位をつける
- リスクの洗い出しと影響評価
- 対策立案と運用体制の整備
- 訓練・検証と継続的改善
ここでは、各ステップについて解説します。
中核業務を特定し優先順位をつける
BCP策定で最初に行うべき取り組みは、自社にとっての中核業務を特定し、復旧の優先順位を明確にすることです。不測の事態が起きた際に、すべての業務を同時に復旧することは現実的ではありません。そのため、事業の継続に不可欠な業務を特定する必要があります。
優先順位を決める際の主な基準は、売上・利益への影響や法令遵守の観点からの必要性、従業員や顧客への影響度などです。
リスクの洗い出しと影響評価
次に、起こり得るリスクの洗い出しと、事業継続に対する影響度の評価を行います。リスクの洗い出しでは、地震や台風などの自然災害をはじめ、サイバー攻撃や設備障害など企業活動に影響を及ぼす可能性のあるリスクを網羅的にリストアップすることが重要です。
影響度の評価では、各リスクが中核業務に与える影響を具体的な数値を用いて検討します。例えば、復旧までにかかる期間や被害によって生じる損失額などを基に、影響評価を行いましょう。
対策立案と運用体制の整備
3つ目のステップは、洗い出したリスクへの対策立案と、実行に必要な運用体制の整備です。例えば、地震によるリスクへの対策なら、重要なデータのバックアップや交通手段が止まった場合に備えたテレワーク環境の導入などが考えられます。
BCP対策の運用体制の整備では、緊急時の指揮系統や連絡体制を決めておくことや、マニュアルの作成などが重要です。
訓練・検証と継続的改善
最後に、BCP対策を実行するための訓練や機能するかの検証、継続的な改善に取り組みます。緊急事態が起きた際に適切に対処するためには、単にBCPを策定するだけでなく、定期的な訓練や従業員への教育が重要です。
また、訓練の実施後に課題を洗い出し、対策の有効性を検証することで、BCPの内容を改善できます。事業規模や社会情勢の変化、法令の変更などにも対応できるように、BCPを継続的に改善しましょう。
現場で押さえるべきBCP対策のポイント
BCP対策を確実に実行するために現場で押さえるべきポイントは次の3つです。
- 発動基準や役割分担の明確化
- 訓練・演習の実践とフィードバック
- サプライチェーンや取引先との連携視点
以下で詳しく見ていきます。
発動基準や役割分担の明確化
BCPを適切に実行するには、どのタイミングで対策を始めるのかを示す発動基準と、各担当者の役割分担を明確にしておくことが重要です。例えば、「震度6以上の地震が発生した時にBCPを発動する」といった基準や、「安否確認をどの担当者が行うか」などの役割を定めることで、現場での初動対応がスムーズになります。
訓練・演習の実践とフィードバック
BCPを策定する際に想定したリスクを踏まえて、訓練や演習を定期的に実施することも大事なポイントです。自然災害やサイバー攻撃など、さまざまな危機への対応をシミュレーションすることで、現場の理解度や対応力を高められます。
また、訓練や演習を実践することは、BCPの不備や運用上の課題を洗い出すためにも重要です。訓練後に参加者からのフィードバックをふまえてBCPを改善することで実効性を高めることができます。
サプライチェーンや取引先との連携視点
BCP対策を行う際は、自社だけでなくサプライチェーン全体や取引先との連携をふまえた視点を持つことが重要です。例えば、自社の設備が復旧できたとしても、仕入先や物流が停止している場合は業務を再開することができません。そのため、重要な取引先のBCPの有無や対策状況の確認、複数の供給ルートの確保など、外部との連携を意識してBCPを策定する必要があります。
BCP対策に関するよくある質問
ここでは、BCP対策に関するよくある質問と回答を紹介します。
BCP対策とBCMの違いは何ですか?
BCMとは「Business Continuity Management(事業継続マネジメント)」の略称で、BCPを適切に策定・運用して事業を継続させるための取り組みを指します。BCPが緊急事態に備えた事業継続や復旧のための計画そのものであることに対して、BCMはBCPの策定を含む取り組み全体を指すことが両者の違いです。
中小企業でもBCP対策は必要ですか?
大企業よりもリソースが限られる中小企業は、災害や事故が発生した際の事業への影響度が大きいため、BCP対策が必要です。BCP対策を行うことで、緊急時のリスクを抑えられるだけでなく、取引先や顧客からの信頼性向上も期待できます。
BCPは法律で義務付けられていますか?
BCPの策定が法律で義務付けられているのは、2025年7月時点では介護事業者のみです。ただし、介護以外の業種であっても、緊急事態への備えとしてBCP対策を行うことが推奨されます。
どれくらいの頻度でBCPは見直すべきですか?
BCPは年に1回以上を目安に見直すと、実効性を高めることが可能です。特に、大規模な災害や社会情勢の変化、組織体制の変更などがあった場合には、BCPを見直す必要があります。
自社に合ったBCP対策で事業継続力を高めましょう
BCP対策は、予期せぬ非常事態が起こった時に事業を継続・復旧させるための重要な取り組みです。自然災害やパンデミック、サイバー攻撃といった幅広いリスクに備えることで、初動対応を適切に行い、事業を早期に復旧させやすくなります。
BCP対策に取り組む際は、自社の中核業務を整理した上で、リスク対応の優先度や方法、役割分担などを明確にすることが重要です。自社に適したBCPを策定し、適切に運用しましょう。
参考:内閣府 防災担当「事業継続ガイドライン」

