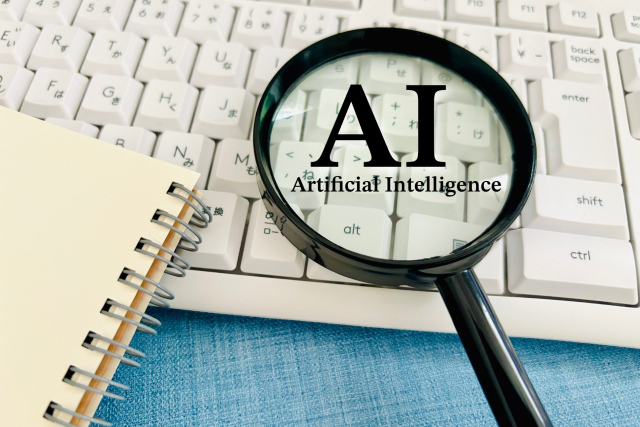
ハルシネーションとは、AIに質問をした時に誤った情報が出力されてしまう現象のことです。ハルシネーションが起こっていることに気付かないままAIが出力した情報を活用すると、業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
この記事では、ハルシネーションが起こる理由や発生しやすい利用シーン、ビジネスにおける実践的な対策などについて解説します。
ハルシネーションとは? 誤情報が出力される理由
ハルシネーションは、AIが誤情報を出力することを指す用語です。学習データの誤りや偏りなどによってハルシネーションが引き起こされます。
ここでは、ハルシネーションの意味や背景、誤情報が出力される理由について解説します。
ハルシネーションの意味と背景
ハルシネーションとは「幻覚」を意味する英単語で、AI用語としては誤った情報を出力してしまうことを指します。まるでAIが幻覚を見ているかのように、誤った回答を出力してしまうことからハルシネーションという用語が作られました。
ハルシネーションはあたかも正しい情報かのように自然な文章で出力されることもあるため、AIが生成した回答が本当に正しいかを確認することが重要です。
なぜAIは事実と異なる内容を返すのか
AIが事実と異なる内容を返してしまう主な理由は、AIが回答を生成する際に参考にする学習データの誤りや偏りです。一般的に、AIはインターネット上にあるさまざまな情報を学習して開発されます。学習データの中に事実と異なる内容や、偏った意見などが含まれていると、ユーザーからの質問に対して誤情報を出力してしまう場合があります。
ハルシネーションが業務に与える影響とは?
ハルシネーションが起きたことに気づかなかった場合、意思決定を誤ったり、信頼関係を損なったりするリスクがあるため注意が必要です。
ここでは、ハルシネーションが業務に与える影響について解説します。
誤情報により意思決定を誤るリスク
AIによって出力された誤情報を信じてしまうと、ビジネスにおける意思決定を誤るリスクがあります。
例えば、新商品の開発を行うための情報収集にAIを使用していて、顧客のニーズに関するデータに誤りがあった場合、商品のコンセプトやターゲットを適切に設定することができません。
また、法律についてAIに質問した時にハルシネーションが起きると、会計業務や人事・労務などの手続きを誤ってしまうリスクがあるため危険です。
顧客や社内との信頼関係への影響
ハルシネーションによる誤情報は、顧客や社内との信頼関係に悪影響を及ぼす場合もあります。
例えば、AIでメールの文章を作成している時にハルシネーションが起きた場合、間違った情報を社内外の相手に送ってしまうリスクがあります。
また、Webサイトに掲載する文章や営業向けのプレゼン資料などをAIで作成する場合も、誤情報が含まれると信頼を損なってしまうためハルシネーション対策が必要です。
ハルシネーションを引き起こしやすい利用シーン
ハルシネーションが起こりやすい利用シーンとして、曖昧な質問や情報の少ないテーマに関する質問をした時が挙げられます。また、専門性の高い内容に関する質問も、ハルシネーションが起こりやすい利用シーンです。
ここでは、各利用シーンについて解説します。
曖昧な質問や情報の少ないテーマ
AIに入力する際のプロンプト(入力文)が曖昧だったり、情報が少ないテーマについて質問したりすると、ハルシネーションが起こりやすくなります。
例えば、「オンライン広告の予算の目安を教えてください」といったプロンプトは、業種や事業規模、広告の目的などが曖昧です。このようなプロンプトを入力してしまうと、自社にあった適切な回答を得られない場合があります。
また、最近リリースされたばかりの商品やサービスに関する質問なども、情報不足によりハルシネーションが起こる可能性があります。
専門性の高い業務領域での活用時の注意点
専門性の高い業務領域でAIを活用する時も、ハルシネーションが起こりやすいため注意が必要です。特に、法律や医療、金融、学術研究といった分野の質問には、AIが適切な回答を出力できない場合があります。
これらの業務領域でAIを活用する際は、出力された内容について専門家がチェックするなどの体制作りが重要です。
ビジネスにおける実践的な対策
ビジネスでAIを活用する場合の実践的なハルシネーション対策として、確認・承認フローを設けることや運用ルール、ガイドラインの策定、教育の実施などが挙げられます。詳しい対策方法は以下の通りです。
出力内容の確認・承認フローを設ける
AIが出力した情報について、内容が正しいかどうかの確認と承認を行うフローを設けると、ハルシネーションによる悪影響を防ぎやすくなります。どのような方法で内容をチェックするか、誰が情報を確認するかなどを決めた上でAIを活用することが重要です。
特に、専門性の高い分野におけるコンテンツ作成やデータ分析にAIを活用する場合は、専門知識を持った人が確認・承認を担当することが推奨されます。
プロンプトの質を高める運用ルール
不適切なプロンプトによるハルシネーションのリスクを抑えるために、プロンプトの質を高める運用ルールを設けることが効果的です。
例えば、社内でAIを使う時のプロンプトの基本的なフォーマットを決めておくと、適切な回答が生成されやすくなります。また、良い回答が生成されたケースや、ハルシネーションが起こってしまったケースについて社内で共有し、プロンプトを改善していくことも有効な対策です。
社内でのガイドラインと教育の重要性
プロンプトに関するルールだけでなく、AI活用全般についてのガイドラインを社内で策定し、教育を行うこともハルシネーション対策につながります。
ガイドラインに記載するべき主な内容は、AIを活用する業務や入力するデータに関する制限などです。また、策定したガイドラインをいつでも確認できるようにしておくことや、研修などで理解を定着させることも重要です。
ハルシネーションに関するよくある質問
ここでは、ハルシネーションに関するよくある質問と回答を紹介します。
ハルシネーションが起こりやすい情報は?
情報が少ないテーマや専門性の高い分野などに関する質問では、ハルシネーションが起こりやすい傾向があります。また、曖昧なプロンプトを入力することも、ハルシネーションが起こりやすくなる原因です。
ハルシネーションが発生する頻度は?
ハルシネーションが発生する頻度は、AIの用途やジャンルによって異なります。業務分野によっては頻繁にハルシネーションが起こる場合もあるため、適切な対策が必要です。
ハルシネーションを完全に防ぐ方法はあるのか
AIが学習データとプロンプトをもとに回答を生成するという仕組み上、ハルシネーションを完全に防ぐことは難しいです。そのため、誤情報が生成されてしまった場合に備えて、AIによる出力を人の目で確認することが求められます。
ハルシネーション理解とリスク回避の実践へ
AIが誤った情報を正しいかのように出力してしまうハルシネーションは、業務に悪影響を与えるリスクがあります。ハルシネーションが起こる主な原因は、学習データの誤りや偏り、曖昧なプロンプトなどです。
AIの運用ルールやガイドラインを策定し、確認・承認のフローを設けることでハルシネーションによるリスクを低減できます。ハルシネーションへの理解を深めたうえで、業務での適切なAI活用とリスク回避を実践しましょう。
参考:IPA「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン」

